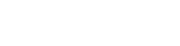社会人経験を経てUCLA Ph.Dへ — Bruin Spotlight: 太田優人さん

日本からの留学生たちは、UCLAの学部課程から修士・博士課程まで幅広く在籍しています。太田優人さんは、経済産業省で社会人経験を積んだ後、2024年秋から政治経済学博士課程(Ph.D)で学んでいます。太田さんに留学までの経緯や、UCLAでの学び、日本同窓会への期待などを語ってもらいました。
自己紹介:
太田優人です。現在、経済産業省からUCLAに留学し、エネルギー・脱炭素関連政策について研究しています。UCLAに入るまでの3年間は、経済産業省のGX(グリーントランスフォーメーション)グループという部署で脱炭素に向けた産業政策などの立ち上げに携わっていました。
趣味はたくさんあるのですが、一つは旅行です。日本では47都道府県中46都道府県を巡り、国外はアジアを中心に20~30か国を訪れました。また、ロサンゼルスに来てからは、離れて暮らす妻子とほぼ毎日ビデオ通話をしたり、UCLAの友人たちと世界各国の料理を作ったり食べに行ったりしています。今秋からは家族もロサンゼルスに住む予定ですので、楽しみにしています!

留学の経緯:
留学するにあたって、日本政府の海外留学支援制度(国費留学)を利用しています。
私は仕事での役割には2つの種類があると考えていて、それは実際の社会事象を動かしていく「プレイヤー」と、社会事象を分析する「アナリスト」です。経済産業省に入る以前から両方の仕事に関心があり、経済産業省で「プレイヤー」として働きつつ、いつか留学を通じて「アナリスト」側の知見も身に付けたいと考えていました。
また、留学前に「カーボンプライシング(排出量に応じた価格をつける施策)」の導入や日本政府初のグリーン国債の発行による投資促進策の立案を担当しており、その中で、政策実務とアカデミア(学問や研究を行う学術界)との様々な「壁」の存在を感じたことも留学に至った理由の一つです。脱炭素に関する政策は、世界中を見ても前例がない状態で全く新しいものを作り出していかなければなりません。そうなると、政策実務における最先端の政治経済情勢の分析と、アカデミアにおける最先端の研究成果との双方が必要になります。アメリカなど海外では政府とアカデミア、民間企業などの間で人的交流が盛んであり、そうした環境に身を置くことで常に最新の情報を交換できるネットワークを築きたいと考え、留学を決めました。
UCLAを選んだ理由:
数ある海外大学の中からUCLAを選んだ最大の理由は、日本の大学の学部時代に10カ月ほど交換留学という形でUCLAで学んだ経験があったからです。
UCLAの魅力はいくつもありますが、まずは政治経済の分野において全米、世界的に見ても最先端の研究を行う教授が数多く在籍しているという点があります。交換留学の際はなかなかその恵まれた環境を生かしきれなかったという思いもあり、今回の留学を通じて教授陣との共同研究なども進めてUCLAのポテンシャルをフル活用していきたいと考えました。
また、このカリフォルニアの素晴らしい気候にも惹かれています。たとえ何か悩み事があっても、カリフォルニアの日差しを浴びると吹き飛んでしまいますね。
さらに、ロサンゼルス、UCLAのカルチャーである多様性も魅力の一つ。さまざまなバックグラウンドの方々がいるというだけでなく、それぞれが互いに尊重されているという文化・雰囲気を感じます。その背景には、もしかするとこの気候の良さも関係しているのかもしれません。また、日本に暮らしているだけでは想像もつかないようなバックグラウンドを持った学生たちと机を並べて議論し合うことは、今までに無い視点を得る観点でとても良い刺激です。
UCLAでの研究内容について:
私が研究対象として主に取り組んでいるのは、環境問題とエネルギー安全保障、経済成長の3つを実現していくための政策を如何に立案し、実現していくかというものです。難しく聞こえますが、つまりは「今の自分たちの安定した生活・社会を守る」ということです。日本で私たちが当たり前と考えている生活は、海外から輸入したエネルギーや輸出先としての海外市場に大きく依存しています。こうした特徴を持つ国は日本を含めていくつかあり、そうした国々が、民主主義の下で、長期スパンの政策を実現していくための政策内容や設計を研究しています。
さらに、企業の資金調達環境やビジネス環境が、各国政府のエネルギー・環境政策によって大きく影響を受けることが多くなっています。したがって、金融市場などの変化がどのように企業行動に影響していくかといった点も研究しています。
加えて、化石燃料依存型の経済が脱炭素化を進めていくことが、経済発展や政治制度の発展にどのような影響を与えるのかといった点についても研究しています。
UCLA、ロサンゼルスの環境の良さ:
上でも述べましたが、UCLAにはいろんなバックグラウンドの人たちが集まっています。UCLAでコミュニティを築くということは、世界中に様々な友人ができ、世界を知るということでもあると感じています。トランプ政権下で移民関係の制限は厳しくなっていくと思うのですが、カリフォルニア、特にロサンゼルスでは少し異なる動きもあり、UCLAも留学生へのケアに力を入れています。
また、カリフォルニア州は、州単体で国家レベルの経済規模を持ちながら、州であるため比較的自由で柔軟な政策を実行しています。こうした条件が揃っているということは、新しい政策を生み出す環境として適しているという見方もできます。実際、カリフォルニア州だけで「カーボンプライシング」を導入するなどしており、カリフォルニアは、今後の政策を研究していく上でも面白い環境だと思います。
UCLAで学んだことを、どのように役立てていくのか:
UCLAでの課程を修了した後は、政策実務とアカデミアの双方の視点から、自分の研究内容を実際の政策立案につなげていきたいと考えています。「政策」というとあまり身近に感じられないかもしれませんが、良い政策が実現していくことは、簡単に言えば、「社会のためにいいこと」と、「自分個人のために良いこと」との両立がしやすくなる環境を作ることだと思います。
さらに、「社会のためにいいこと」の中には、今を生きる私たちだけでなく、その子どもや孫といった将来世代のためにいいこともあります。私たちの世代が、将来世代により良い社会環境とそれを更に良くしていくための手段を残すための「投資」が必要であり、それを社会全体としてより実行し易くするというのも、政策の重要な役割です。UCLAでの研究を生かし、こうした理想を少しでも実現していくことが出来ればと考えています。
UCLA日本同窓会へのメッセージ:
同窓会は、異なるバックグラウンドを持つ方々とUCLAという共通のつながりを通じて交流できる貴重な場だと感じています。普段の生活では出会えない方々と出会い、相談し合える機会を持てることに大きな意味を感じました。これからもこのコミュニティを大切にし、関わっていきたいと思います。